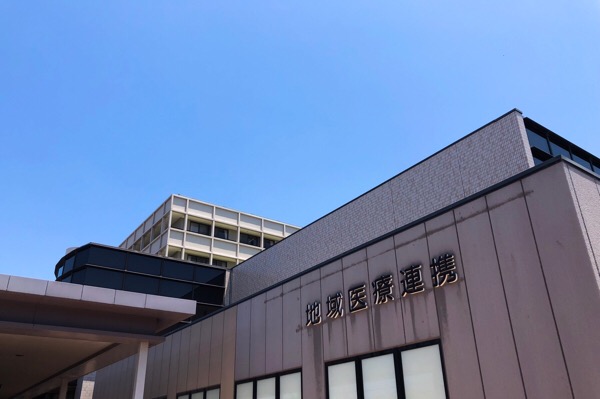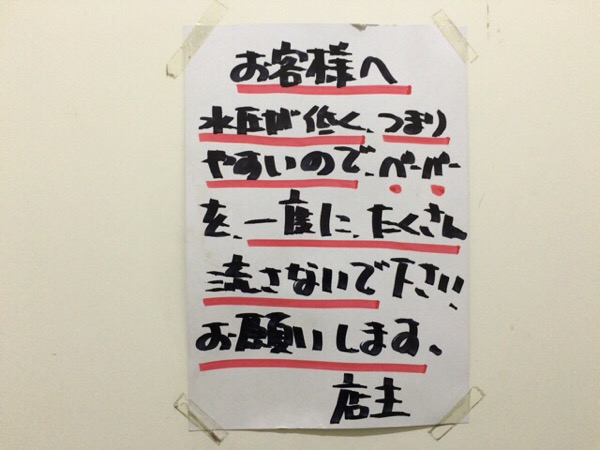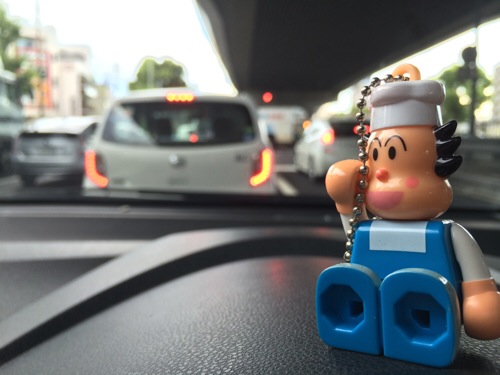コロナで入院したとき、すでに僕はもう体力が落ちていて、いわゆるレッドゾーンの向こう側へは車椅子に乗って運ばれていった。
廊下からそれぞれの病室を覗くと、思ったよりはベッドに空きがあるように感じた。入院できる数には限りがあると聞いていたものの、明石ではまだ余裕があるのだろうかと思ったくらいだ。
そしてこの考えは浅はかであったとすぐに気付かされることになる。
みるみる症状が悪くなっていった僕は、酸素吸入が必要な状態に陥ってしまった。
こうなるともう、「自分というひとりの人間から生きる力を最大限引き出すためには」ひとりふたりの医療看護スタッフの介添えではどうしようもなくなるのだ。
入院しているから、具合が悪いから、だから寝ていれば良いというものではない。
・シャワーを浴びれない全身を拭いてくれたり
・薬を飲むたび、誤飲しないよう観察していてくれたり
・高熱が続いて不安なとき、話し相手になってくれたり
・すこしでもご飯が食べられたら、それを褒めてくれたり
あぁ、なんだったらもう、たまたまコロナ病棟にいた僕の幼馴染の看護師は、こっそり髪の毛を洗わせてくれたり、パンツの洗濯までしてくれたりした。
窓を開けることのできない病室。気が滅入りそうになっていると、車椅子の僕の背を押してもらって、廊下で風を感じさせてくれたりもした。
「それは禁止されている」ではなく、僕が望むことは、可能な限り実現しようとしてくれた。そうやって僕の生きる力を引き出そうとしてくれたのだ。
だから僕はいまここにいて、これを書いている。
あの日、僕の尊厳と気力を最大限尊重してくれた、ひとりではなく、たくさんの明石市民病院の医療・看護スタッフの方々。「病床」という響きにはつい、「ひとつのベッド」を思い浮かべてしまいそうなものだが、実際にはそんなことはない。
ひとつのベッドに身体を横たえた人間が生きようとするためには、何人もの献身的な努力があったということを、僕は生きることができたからこそ伝えたいと願うのだ。
だから思う。「病床」という言葉の違和感を。
報道などで「病床に空きがある」という表現を耳にするたび、僕はこれを「看護チーム」と置き換えてみてはどうかと思ったりする。「場」ではなく「チーム」があるから、ひとりの命を救えるのだということ。「ひとりの命を救うためには、ひとつの場が必要なのではなく、大きなチームが必要なのだ」ということ。
退院して以後も、僕は病院に通い、仕事でも色々なトラブルに見舞われ、けっして順風満帆というわけではない。
ただ、ネガティブになってしまいがちな出来事に遭遇したとき、まず最初に「生きよう」と舵を切れるのは、あの日あの時、懸命に、僕のわがままにこたえてくださった看護スタッフの皆さんの顔が浮かぶからである。
命を粗末にはしない。
だからこそ伝えたいこと。
僕の命は、とてもとてもたくさんの人たちの想いと行動によって繋がれたのだ。