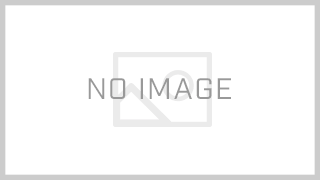東野圭吾さんの『同級生』読了。
東野さんの小説の魅力は、霧のかかったようなストーリーの中で、突然眩しい光が
差し込んでくる、そんな衝撃にあるのかもしれない。
今回の本も、それぞれに「秘密」を抱えた人間たちが、靄の中で真相を求めながら
探り合いをしていく、そんなスリルの如きものが味わえた。
青春はいつでも真っ直ぐだ。
あっという間に燃え上がる。駆け引きなんて知らずに、ぶつかっていくときも真正面から。
自分なら、「僕です」と言えたかどうか。
そして、仮に「僕です」と答えられたとき、その想いはどこから生じただろうか。
罪悪感? 良心?
それともやっぱり、物語の中に出てくる「俺」のように、「反発心」がそうさせたかな。
「罪の意識」って、そんなものを持たずに純粋に行動って出来るだろうか。
僕は僕の「どちらがマシか」という選択においてのみ、この道を生きているような気がして
ならない。
「青春の葛藤」とも言えるこの本に触れて、改めて、今の自分の弱さを思い知らされた。
手のひらの砂は。
波に流され、風に飛ばされ、同じようにして形を止めることはない。
やがて太陽も地平線。冷たい空気が辺りを包みだして、胸の真ん中に切なさを覚える。
目を細めている、燃えたぎるような炎を覚えながら。
でも、届かない。 この腕も、この声も。