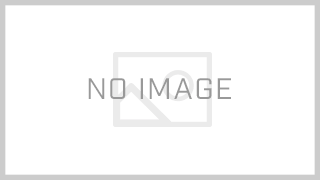「地味にショックだ」と言う人がいて、ではこの人にとって「地味にショック」と「普通にショック」そして「派手にショック」の境目はどのあたりにあるのだろうと考えていたら、そんなショックなことなんてどうでもいいじゃないって気分になりましたね(あかん)。
— 西端康孝 / 川柳家・歌人・コトバノ (@bata) 2017年11月19日
意味を添えて言葉にすることもあれば、語感だけでその言葉を用いることもある。
たとえば「ヤバい」なんて言葉は、意味よりも勢いだろう。文字になった表現のすべてが「ヤバい」になってしまうのは確かにヤバいのだろうけれど、会話をしているときの「ヤバい」は、ある程度の驚嘆や感動を理解できるものなら、使っても構わないと思っている。「おいしい」「ヤバい」で伝わるものを、「これはかつて口にしたことのあるどの食材よりも柔らかく、甘く、それでいて懐かしく、優しい。僕はこの感動のために今日までを生きてきたのかもしれない」なんていちいち言葉にしていれば、一瞬で面倒な人間だと思われてしまうことだろう。本当の意味で「ヤバい」奴になってしまう。
会話をしていると、この人はいま、もっと難しい言いまわしを思いついたのに、この場の最大公約数を選んで、あえてこの言葉を用いたのだな、と気付くことがある。カタカタではなくあえて「たとえば」を使ったな、とか、四字熟語ではなく「自虐」で悟らせたな、とか。
おお、かっこいい。なんて頭の良い人なのだろう。
ぼ、ぼくも、あなたのその配慮に気付いた人なのです。そのうちのひとりなのですが、えっと、気付きましたよ、今の配慮。気付きました気付きました。えーっと、挙手しましょうか? はいはーい、僕、気付いてる側の人間ですよー。うほほーい。
と、アイコンタクトなり、気付いてる空気的なものをある程度醸し出したところで(あ、この気付いてますよオーラが嫌な奴オーラなんだった)とようやく理解するのである。だが時すでに遅し。このうほほーいオーラを我慢できないところがダメなところだ。
言葉は面白い、同じことを伝えるのにも表現は人の数だけある。正解はないし、上も下もない。配慮に満ちていることもあれば、乱暴なこともある。すべて、人を表している。うほほーいは少し痛いけれど、それだって僕の個性なのだ。
表現を臆することはない。どんな人格も、どんな商売も、伝えていかなければ、伝わらない。伝えないのは存在しないのと同じ。痛くても良いではないか。その傷もまた、誰かが僕を、僕だと認めてくれる。
伝えるということ、伝わるということ。
そこに在るということ。
僕は痛くて弱いなりに、その価値を伝えていきたいなぁと思っている。