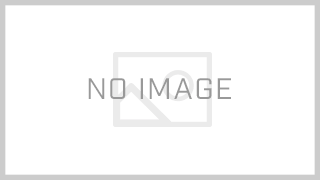知人友人家族、繋がりのある誰か。
病気になれば、当然に心から快癒を祈る。元通りになることを信じて疑わない。ところが、時々、カウントダウンの針の音が聞こえてくることがあって、その音に従うように会いに行ってしまえば「もうこれが最後になるからしれないから」という心を見透かされてしまうのではないかと思ってしまう。つまり「信じてる」のに「信じてない」。
そうして僕は、やっぱり、信じている自分を信じる風に振る舞うことになる。
信じるということは祈りにも似て、不安の波は不安のカタチのままに相手の結果に作用してしまうことがあるのではないか。僕は昔からそう考えることが多く、こういうときの自分の心境に苛立ちと戸惑いを覚えてしまう。それでいいのか、と、何度も自問自答を繰り返してしまう。
出会った方々のひとりひとりは、自分を構成しているパーツのひとつひとつだ。欠けることはこれっぽちも想像しないまま、突然を迎えて、僕のすべてが止まるような錯覚を覚えてしまう。何度泣いて何度叫んだことか、僕の骨たちは絶叫の振動を忘れることはない。
会者定離、生者必滅、生死不定、生死無常。
突然の前に、もっといえば、日常であるときから、当然に。会いにいくようにしなければならないのだろうね、きっと。そうするべきだったんだろうね、もっと。