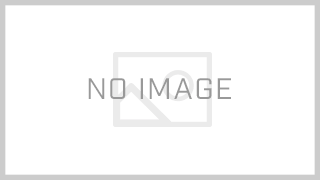自殺者の三万人を言いしときそのかぎりなき未遂は見えず
吉川宏志
燕麦―吉川宏志歌集 (塔21世紀叢書)
新しい看板のまま、もう、営業をしている気配のないお店。
出来てすぐに潰れた場合もあれば、最後の最後に起死回生を狙って看板を改めたところもある。印刷や販促の仕事をしている僕のところには、命の縁を背にした人たちが相談に訪れることがあって、その施策が間に合わず退場を余儀なくされた方もいる。残された僕たちは、ここで、ずっと破れそうな気持ちを生きていくことになる。死にたいと思っても闇、渡って、突きつけられて残った人たちも闇。与えられた命の期限を早めて川を渡ることは罪だというけれど、せめてそんな風ではあってほしくないと願う気持ちと、荷物を置いたままに渡った軽さに、苛立ちをぶつけたい気持ちとがある。貴いのに、軽い。命は純白の風船のようだ。
渡る手前で踏みとどまって、絶望に心身を削がれながら生きている人たちの数。昨日は違っても、今日は曇って、明日には降り出すかもしれない空と風を過ごしている自分たちに、他人事であるとはいえない。闇の無い時代なんてなかった。ただ、闇の次の光の順番をむかしはもっと期待しても良かったような気がする。今はなにが違ってしまったのだろうと、蒼い息を吐き出しながら考える。自分だってもっと、急がなくてはきっと。