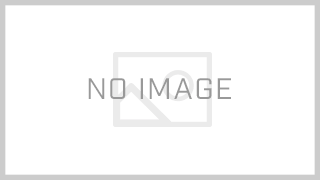朝までは元気だった人が、自ら命を閉じて、夕方。
警察の検視が終わって落ち着きを取り戻した場所に向かうと、何事もなかったかのように人々は行き交い、家路を急いでいる。残留思念のようなものを感じ取った気がして、絶つ瞬間のそれではなく、なんの不安もなく笑ってこの道を歩いていたのであろう本人の行動を追体験する。ある瞬間から苦悩は心を支配し始めて、とうとう、その人は逃げることができなくなってしまった。残された人たちは涙も忘れている。きっとそれくらい、その瞬間はなんの前触れもなくやってきたのだろうと思った。
あっちとこっちを分ける線は、子どもの頃に考えていたよりも身近にあるような気がする。ただ、まだしばらくこっちを過ごす人間は、あっちへ行く命の渡り方にたくさんの意味を重ねてしまう。そうしてその意味は、ときどき、こっち側で生きる人間に、黒くて重たい気体になってダメージを与え続ける。だから僕は、そんな渡り方をした人への告別は行わないことに決めている。君が抱えた大きな傷を、もっと大きくしてこっちに残してどうする。どんな居心地で、そっちからこっちを見てる。
君のいた場所から南にくだって、角を曲がる。洒落た食器を売るお店に来て君は、どんな料理が並ぶのを想像して笑ったんだろう。