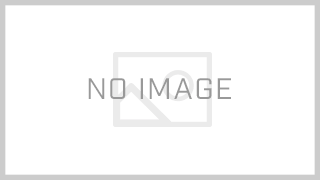三月の十日の新聞手に取れば切なきまでに震災前なり
中村偕子
変わらない空 泣きながら、笑いながら
東日本大震災を経験した五十五人の共著である短歌集変わらない空 泣きながら、笑いながらを読んだ。どの歌も淡々と描写されている分だけ、言葉にはできない行間の無念が重たい。すべての歌に英訳が添えられているのはこの震災を後世に世界に伝えたいという編者の想いもあって。
picking up
a newapaper dated
the tenth of March
heart breaking, that it was
before the great earthquake
阪神淡路大震災のとき、僕は大学受験を目前に控えた高校三年生だった。震災の朝を境にして、それまでの当たり前は当たり前でなくなって、それまでの無関心は関心へと変わっていった。
瓦礫の街、交通網が寸断された世界で代替バスを待つ。僕を受験生だと気付いた人がいて、列の前の人たちに大きな声で訴えてくれた。「この子、今から京都まで受験行くねんて。バス待ってる間に風邪でも引かせるわけにいかへんやん。先、乗らせてやってもええよな?」
神戸を離れて東へ向かうにつれ、屋根のブルーシートは見かけなくなっていった。宿についてすぐ、風呂の蛇口からお湯が出ることに感激した。ホテルの人は「特別ですよ」と言って、夜食の差し入れをしてくれた。みんなが僕に特別をしてくれたのは、あの日からしばらく、ずっとのことで、とても不思議な時間だったのを覚えている。日常は日常ではなくなってしまったけれど、そこにある特別にたくさん触れられたのは、震災が与えてくれたものだった。
震災のまえ、そして、あと。「たくさんのひとたちに」「たいへんなことがおこった」という事実は知っていても、ひとりひとりのその後や今は知る由もない。神戸からの20年。僕たちは、いろいろのあとの今を生きて笑っている。なにができるわけでなくても、ただ生きている。それだって「そのあと」の軌跡として意味があると考えるのは都合が良すぎるのかもしれないが、生きているというのはそれくらい、特別と特別の積み重ねなのだと感じるようになった。