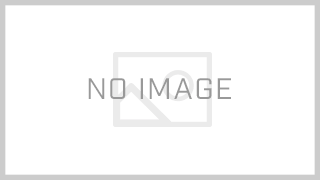犬だとか、父親だとか、親戚だとか、家族だとか。
そんなすべてがぎゅっと存在していたのは、僕にとって90年代。中学生や高校生の頃の放課後は永遠だったし、夢や愛なんてことは星の数以上に語り合った。メールはもちろん、ケータイという文化も一般的ではなかった頃で、ある時間帯を過ぎれば夜は静か、果てしない空想に意識を飛ばしては空が白くなるまで詩や手紙を書いたり、作曲をして過ごしたりした。
Kiss FM KOBEという地元のFM局が、夜中になるといつも、胸の締め付けられるような切ないジングルをラジオから流した。それはSuzanne CianiのDriftingという曲で、神戸を過ごした人ならば、一度は耳にしたことがあるのではないかと思う(リンク先から試聴可)。
大人になった今も、僕の夜型の生活は変わることなく、明けるまでの時間を ――いまは現実に追われていることがほとんどだけれど ぼーっと過ごすことが多い。
そしてなんとなく、このSuzanne CianiのDriftingという曲をiPhoneから再生しては、懐かしい声や感触を思い出してみたりする。「ぎゅっと存在していた」を象徴する曲だからなのか、すこし、切なさを感じたあとに、じわっと温かくなる。そして朝がくる。このリズムで日々が繰り返されていくことが僕にはとても心地良い。
徒然なくこんなことを書いて、特に何かを伝えたかったわけでもない。「こんな原点に回帰することも大事ですね」という教訓っぽい話をしたいわけでもなく、もしかすると、同じような時代感覚に生きる人が、同じようなキーワードでネットの海を泳いで「そうかこういう曲名だったのか」と辿り着くのではないか、と思ったのかもしれないし、「同じ曲を聞いてこんなことを感じた記憶がある」という共感が欲しかったのかもしれない。かつて同じようなことを話題にした気もするけれど、僕の思い出の枝にぶら下がる存在のひとつで、信念だとか、志だとか、自分が話題にしがちなこととは距離があるような気もする。だから過去を探してリンクするようなこともしない。
夜から朝へ、静寂の点、満ちていく線。この時間特有の「音」について、ふと、書いてみたくなった。みんなみんなのいた、そんな頃のことにも触れて。