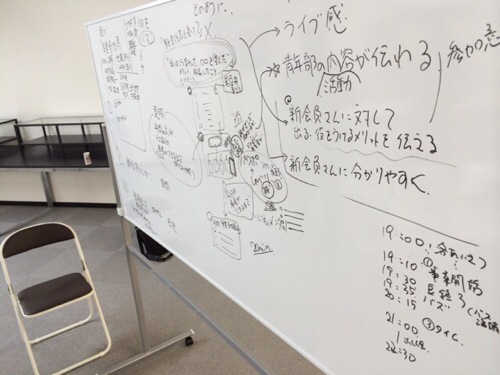かの時に言ひそびれたる大切の言葉は今も胸に残れど
石川啄木
一握の砂
血圧や呼吸、心拍を伝える集中治療室のモニター。僕たちは父の顔をみて危機を知ったのではなく、赤くなった数字の色と響き渡る電子音によってその状態にあることを知ることになる。医師たちの真剣な表情と動作のひとつひとつに緊張が走った。
ドラマならここで「死ぬんじゃない」と声を出すのだろう。現実にはこの場面、僕たちは何の声もあげることができない。「死ぬなよ」と伝えることは「死にそうなんだ」と自分がそう思っていることを認めてしまうことになる。「ドラマじゃあるまいし簡単に人を殺すんじゃない」とあとで笑われそうで、しばらくは黙って見守っている。まさかそんなはずはないと心に言い聞かせて、右手と左手、潰れそうなくらいにぎゅっとして待っている。
やがて心臓マッサージが始まる。ここで僕たちは絶叫を始めた。亡くなった直後に書いた日記で、僕はその様子を「病院に響き渡るくらい」と表現している。死んでほしくなかったし、死ぬはずはないと思っていた。だからまだ、この段階でも照れがあって、生きている間に伝えるべきひとことを残してしまった。僕はいまもずっとその後悔と生きていて、死んだら一番に謝って、そしてちゃんと伝えようと思っている。その日までをちゃんと生きていこうと思っている。
伝えて変わることもあれば、伝えたところで事態に変化は生じないこともある。それでも、伝えて軽くなることならば言葉にするべきだし、伝えられて嬉しいたった二文字は、ちゃんと受け止める方がいいんだろうって思ってる。胸に残して詩に歌い続けたところで、あの日、声にできなかった後悔にはずっと勝てない。
何年かが過ぎて、色褪せるものではなくて。過ごした日々の輝きばかりが増していく。だからこそ余計に、臆してはならない二文字。