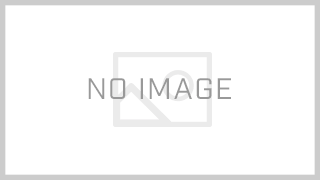歌人の穂村弘さんは、この歌をとりあげて次のように評している。
「クーラー」「土のにおい」「遠雷」は、それぞれ触覚、嗅覚、聴覚に対応している。視覚以外のいわばマイナーな感覚が連動することによって臨場感を生み出しているのだろう。
短歌や川柳の面白いところは、限られた字数のなかで、写真や映像以上に生々しい想像を与えてくれることにある。
蝉の声を掻き消していく雨の音、雨の音を吸い込んでいく土。遠くに光る雷の音は、ここまでは響いてはこない。クーラーは微風、風に乗るにおいがアスファルトでないということは、ふたりは雨が降り出す前から、土に車を停めて何かを話していた。川原だろうか公園だろうか。会話は広がりを見せたのか、それとも、音のないままに光る雷が、ふたりの関係を暗示しているのだろうか。車を打ち付ける激しい雨の音があるはずなのに静寂を感じるのは、漏れてくる土のにおいだけが存在感を示しているからだろう。
安心に包まれた空間であると想像することも、緊張の走る間合いであると想像することも、読み手の自由。それが短詩文芸ならではの楽しみ方。
8月の雨はエネルギーが飽和した瞬間に溢れ出す、だから嫌いじゃない。夕暮れに汗とため息を洗って、もう少し頑張れという顔をして軒下から街中に連れ戻してくれる。暑がりなアスファルトも優しい服に着替えを終えた。
入れ替わった空気、月にバトンが渡るまで。何百回と横顔を眺めたような気もする、でもあるいは、ほんの数回のことだったのかもしれない。この時期のことは何度も詩に描いてきたけれど、波や汽笛やテトラポッドの感触を覚えているだけで、永遠の約束は言葉にもならない。薄い誓いを繰り返してばかりだったのか、それとも、淡い自分の傷付きやすさを知っているからなのか。