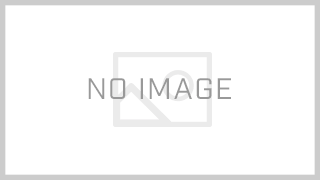文芸の世界にも写実主義とロマン主義とがあって、虚構であってはならないという意見と表現のなかで想像は自由であるという意見が対立する場面をよく見かける。どうであれ、読み手の想像力に委ねることに変わりはなく、僕は想像の自由があって構わないと考える側の人間だ。僕のなかには鬼だっていれば、人間の言葉を自由に操る動物たちだって住んでいる。触れたことのない生き物や感情が行間に見えたとしても、それらのフィクションには笑ってお付き合いいただきたい。
自ずとそんな同士のご縁をいただくことが多くあって、言葉の紡ぎ方と行間の伝え方について持論を話す機会がある。想像に向けられる邪推に苦しむのは誰も皆同じで、理解してくれる層に対してだけの発信になってしまえば、伝えたい主張したいという想いとは裏腹の失速となって世界は広がりを見せない。言葉は時に強く、弱く、理想とのギャップに苦しむ人が多いのも事実で、僕たちはいっとき、「想像の世界から離れて、現実だけを直視した」表現の方法を選択する。冷たい風が止むのを待って時々歩き出す、そんな風に形容した人もあった。

文学館に足を運んで、ガラスケース越しに当時の作家たちの原稿を眺めて過ごすことがある。今とは違って、言論を弾圧されることの多かった時代。ペンを執ることを諦めず、されど最後には自死を選ぶ作家のいた理由も今なら少しだけ理解できるような気がする。理想を抱いた作家たちは、現実との大きな隔たりの沼で重たいクロールを強いられたのではないだろうか。ネットという手段のなかった時代、沼は闇の下にあって、その方向も横に並ぶ人たちの存在も認めることができない。ただ、ただ、泳いで、向かっているような気持ちを軸にして、己を納得させていたに違いない。
もちろん、それもまた、僕の想像でしかないのだけれど――。
想像に働きかける仕事をしながら、想像の曖昧さに苦しむことがある。いまは世界が開かれた分だけ自由なのかといえば、晒されているという感覚の危うさもあって、どこか不完全なままを過ごしているような感覚も否めない。そうして、届かないままをぐっと押し殺していたりもする。