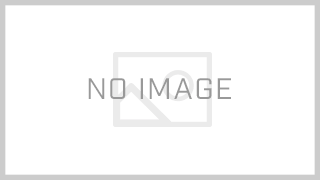生業のために言葉を選んだのではなく、伝えたくて大切にしてきたものが生業となっただけのことだ。想像を喚起する言葉、または詩歌。すべてを書いてしまえば説明書になってしまう。たとえば「雨風に耐えて窓を開けているのは、誰かの想いを繋ぎ合うため」と書いて、全身を赤くした奴のことを伝えてみようと試みる。遠回りのようでいて、心を揺らすために必要なこの試みは、読み手を信頼するからこそ出来る一手。いつも「響け伝われ」と念じながら風船の行方を見守っている。
仕舞い込んでおきたい物語を白日の下に晒す言葉は嫌いだ。それは乱打、それは暴力。想像という共有は生まれず、好奇心の燃料となって心を傷め続ける。寒くて震える人が纏う毛布を剥いで、僕たちには何が満ちるのだろうと考え込んでしまう。彼もまた、我と同じ人であって、ここから未来を生きていく必要がある。 僕の放った一瞬の言葉は、彼の永遠の重さとなって跳躍を妨げてしまうことも有り得る。それも想像。許されたいように許して生きていく方が、きっと人生は穏やかなものとなる。
言葉は豊かで優しく、そして恐ろしいものでもある。残るもの。だからこそ、ときに大胆に、ときに慎重に言葉を選んでいきたいと思う。